文・宮森健次/イラスト・儀満悦子
こどもと落語
松江噺乃三種盛
落語教室を始めた時からオリジナルの演目をもちたいと思っていましたが、松江歴史館から松江城などにまつわる史話や伝説を演目にしてもらえないかという思わぬきっかけを与えられ、願いがかないました。それが演者と聴衆から愛されるネタになるかどうかは、高座にかけてみないとわかりませんし、並大抵のことではないと覚悟しております。ただ少なくとも、作品の練度をあげていく足場はできたわけで、それだけでもとてもありがたいことです。
年明けから、寄席や稽古で子どもたちがかけ始めましたが、そのしゃべる様子やお客様の反応からたくさんのことに気づかされています。意に反してウケたりウケなかったりすると、その理由が思い当たり、なるほどそういうことかと納得します。お客さんや子どもたちに一つ一つ添削してもらっているようなものです。子どもたちそれぞれのアイデアもこれから加わってくるでしょう。それもとても楽しみです。
書き直しながらつくづく思うのは、古典落語の完成度の高さです。さりげない情景描写や小さなセリフの一つ一つに必然性があって、お客様のイメージが澱んだり脇へ流れたりしないよう細心の工夫が積み重なり、オチへと至る。まさにたくさんの演者で作り上げた知恵の集積なのです。
さて、昨年の春先から始めた小泉八雲の怪談、夏から始めた出雲弁落語、冬からの松江城物語、こうして並べてみるといずれも松江ゆかり、よそでは決して得られぬものですから、三つをまとめて何か名付けてみたくなりました。セット、詰め合わせ、など思い浮かびましたが、どれも言葉におもしろみがなく、あれこれ考えた末に「松江噺乃三種盛(まつえはなしのさんしゅもり)」としました。すぐに三色丼のような絵がうかんできましたので、どんぶりの中でそれぞれの登場人物が勝手にしゃべっているようなイメージを伝えて、イラストを描いてもらいました。次ページのがそれです。
このところ、この三種盛の注文がよく入ります。看板メニューになりそうです。

王子のきつね
以前、本欄にたぬきについて書きましたが、数において及ばないもののきつねもまた落語の重要なキャラクターです。その代表と言えば、「王子のきつね」でしょうか。きつねが化けるところを目撃したある男が気づかれていないのをいいことにきつねの方をだまして、さんざっぱら飲み食いをします。そのせいできつねがひどい目に遭ったと聞かされたこの男、さすがに気が咎めて後で謝りに行くという噺。たがいに化かし化かされのやりとりや、子ぎつねの登場もあって、どことなくほのぼのした感じのする傑作落語です。
永井荷風の初期の作品に「狐」という短編があります。幼少期の実体験を元にしたとおぼしき作品ですが、これを読むと当時の市井の人たちがきつねに対してどのような感情を抱いていたかよくわかります。家の敷地内に巣穴を見つける話ですから、今よりうんときつねは近しい存在でした。もともときつねは人の生活圏に近い動物だそうですが、私たちが野生のきつねを見かけることはまずありません。
奥出雲で暮らしていたとき、一度だけばったり遭遇したことがあります。ちょうど今ごろ、雪の降り積もる真冬のことでした。知人宅ですっかりご馳走になって、夜中にいい気分でとぼとぼ峠道を歩いて帰っていたところ、街灯の下で何やら跳びはねているのが目にとまりました。雪に覆われた田んぼが広がり、人家も闇に沈んで、そこだけスポットライトを灯したように明るい。近づくにつれて、きつねだとわかりました。
きつねの方は雪に吸われた足音に気づけなかったか、私がそばにいるとも知らず、雪の上でくるくると回ったり跳んだり踊り続けていました。街灯と雪明かりを身体中で散らして、きつねは黄金色に輝いて見えました。私は足を止めて、長いこと眺め続けました。というよりすっかり見とれてしまい、凍てつく夜だというのにその場を離れることができなかったのです。古来よりおびただしく語られ作られてきたきつねに化かされる話、王子のきつね、新美南吉の童話、みんな生まれるべくして生まれた話なのだと思わずにはいられません。
「王子のきつね」は、東京都北区にある王子稲荷神社にちなんだ噺です。きつねは言わずと知れたお稲荷さんの使い。忌み嫌われる一方で神様の使いとして尊重もされる、分断化の進む世界の真逆に住まうユニークな存在です。それだけに、子どもたちにも出会ってほしくて、いつかとりあげようと思っていたネタの一つでした。ただ、今ひとつ踏み出せなかったのは、子どもたちにとって王子という地が、あまりになじみがないからでした。でも、古典落語の出雲弁バージョンづくりを続けている中で、はたと気づきました。松江のお稲荷さんを舞台にすればできるんじゃないか、と。格好の素材がありました。小泉八雲が好んで通った雰囲気抜群の城山稲荷神社。脚本は一気にできあがりましたが、さて実現するか否か。2025年1月1日、私は初めて初詣にこの神社を選び、城山のきつねが高座にかかりますようにと祈願したのでした。

無精猫

無精者(ぶしょうもの)、今の言葉で言えば「めんどくさがり」でしょうか。落語の国では欠かすことのできない大切な住人です。この無精者たちが何をするか、また、何をしないかでりっぱな噺になるのが落語らしいところです。
ある無精者親子がおりました。もし無精オリンピックがあったら金メダルまちがいなしの筋金入りの怠け者親子です。何せ、家が火事になっているのに逃げるのがめんどくさい人たちですから。死後も無精っぷりは何ら変わらず、地獄の王閻魔様の前だろうと徹底して無精を貫きます。権威を茶化してはばからないのも落語のもつたまらない魅力の一つですが、中でも「無精猫」の作者は相当にアナーキーな感覚の持ち主だったろうと思われます。
登場人物は3人だけ、加えて民話の定型とも言うべきリフレインで構成されているので、扱いやすいネタです。以前小学校で落語をしていたときも子どもたちに積極的に勧め、先輩から後輩へ受け継がれる噺の一つとなりました。だから当然当塾でも扱うことになるだろうと思っておりましたが、これぞタイミングの妙とでも言いましょうか、予期せぬ方向に噺は転がりました。というのは、この噺を勧めた子がそのころかけていたのが、ちょっとだけ出雲弁を入れたネタでした。落語はもともと江戸と大阪を発祥とする地方芸能なので、出雲弁の落語というのは存在しません。しかし、まず語り手ありきの話芸ですから、どのようにアレンジしても自由なので、一部改編して出雲弁を挿入していました。寄席でお客様の反応を見ていると、毎回出雲弁部分が突出して強い。「また、あの噺が聞きたい」とリクエストがあるほどです。それならば、と全編出雲弁にチャレンジした最初の作品がこの「無精猫」です。
出雲弁に囲まれて育った私とはまったく異なる言語環境で育つ塾生ですから、まるで外国語を習得するようなものです。仕上げるまでにはずいぶんな骨折りだったと思いますが、やっぱり反響は大きかった。出雲弁を知らない世代も含めて「おもしろかった」の声がたくさん寄せられたのです。私も改めて方言の持つパワーを思い知らされました。
もともと上方の小咄だと思われる本作を、プロが語るのを一度だけ聞いたことがあります。また、これまで子どもたちが寄席にかけたのは共通語に直したテキストでした。そのどれと比べても、出雲弁「無精猫」はおもしろい。これは出雲弁特有の音やリズムが噺のおもしろさを増幅するゆえではないかと思うのです。言葉を伴わない音楽が細かな感情を表現できるように、出雲弁は怒りや悲しみの言葉にさえおもしろさを加えます。
聞いていた他の子たちもやってみたくなったようで、現在何人か取り組んでいます。出雲弁おもっせがや、箪笥の奥にしまっちょかんでどんどん使っちゃらこいという子どもたち、こんな形で伝承に少しでもお役に立てたらほんとうにうれしいことです。これから寄席にかける機会も増えそうです。どうぞ聞きにいらしてください。
小泉セツ

以前、当欄で「怪談」のリクエストがあればぜひ、とお願いしましたが、これも「ばけばけ」効果でしょうか、続々と「怪談と落語のセットで」というオファーをいただいています。この夏から寄席のラインナップの中に「怪談」を入れて、お客様にお届けしています。決して笑って楽しむという話ではありませんが、息を詰めるようにして耳を傾け、終わるとため息をもらすように感嘆してくださいます。子どもたちも私もさらに経験を積んで、滑稽話と怪談どちらも相乗効果で楽しんでいただけるように努めたいと思っています。
小泉八雲の『怪談』が出版されて120年にあたる今年は、八雲の没後120年でもあります。つまり最高傑作の誉れ高い『怪談』は、まるでその命と引き換えのようにしてこの世に誕生しています。
最近『八雲の妻―小泉セツの生涯―』(長谷川洋二著・今井書店)を読みましたが、中で『怪談』の成立過程についてもいくつか興味深いエピソードが紹介されています。セツが大きく貢献したことは有名ですが、読むと実際は、素材集めはもとより、あらすじを書き、脚色し、語りの工夫を凝らし…、ああここまで尽くしたのかと畏怖の念を覚えるほどでした。
もともとセツは大変な物語好きで、誰彼構わず「お話しすてごしなさい」とせがみ、二十歳過ぎてもその調子だったとあります。物語に対する類い希な感受性の持ち主二人が練り込み磨き上げた数々の作品を身近に感じながら読み、語れるというのは何ともありがたいことです。
セツは東京に出てから歌舞伎にはまり、頻繁に通ったようですが、落語との出合いも当然あって、八雲は大名人三遊亭円朝の高座を聞きに行くように熱心に勧めています。夏目漱石はじめ多くの文人たちが円朝には大きな影響を受けていますが、セツもまたその一人でした。円朝の語りにも学びつつ八雲に語ったものと思われます。ただし、セツの言葉は明治の濃厚な出雲弁で、ところどころにその痕跡を見ることができます。言うなれば、セツの語りを通して松江の風土や文化が八雲作品に埋め込まれたわけです。八雲を覚え、語る当教室生は知らず知らずそれを身につけているということになりましょう。

同書からもう一つエピソードを。奉公人の一人お咲が嫁ぐことになり、親代わりのように育てたセツが式の前夜に結婚生活の要諦を説く話が出てきます。お咲が終生忘れることなく守ったというその言葉とは、「人間は、どんなにいい姿をしていても、その人の言葉一つでわかります。決して言葉は崩してはいけません」というものでした。
抜け雀

名人が登場する話といえば、真っ先に思い浮かぶのが中島敦のその名も『名人伝』。天下第一の弓の名人を志した紀昌の成長物語。何度読んでも飽きることのない無類のおもしろさで、若かりしころは、講談調にして教室で語ったものでした。道具立てとしては今のヒーローものとそれほど変わりはないと思いますが、中島敦の格調高い美文が説得力となって夢の世界に誘ってくれます。
落語の中にも名人が登場する話は数多くあって、左甚五郎はじめ有名無名さまざまな名人たちの逸話が語り継がれています。落語の名人ものは、作品に命をふきこむことができる、という点で共通しています。木彫りのねずみが動く、大黒さまがニッと笑う、竹の水仙が咲く、というように。落語ばかりでなく、雪舟が涙で描いたねずみや絵姿女房やこの手の話は古来から枚挙に暇がありません。あり得ない話というのはわかっていてもあり得るかもしれないと思わせてくれる語りや文体を昔から人は大切にしてきた、ということなのかもしれません。
『抜け雀』は、数ある名人ものの中で、私がいちばん好きな話です。厳密に言うと、古今亭志ん朝のそれでないといけません。さらに厳密にすると、40年以上前にFMラジオで聞いたそれをもっていちばんとしています。一文無しで旅をしていた絵師が宿銭のかたに衝立に雀の絵を描きます。これは、いやがる宿屋の主人を脅しつけて無理矢理描くのですが、志ん朝の造形する宿屋夫婦がまさに名人芸で、このあたりのやりとりがおもしろいことこの上ない。せっかくの売り物の衝立を汚した、と不平たらたらの主人でしたが、絵師が旅立った翌朝雨戸を開けると、差し込んだ朝日に雀が絵から抜け出していくのを目にします。ここから始まるこの絵の数奇な運命と宿屋夫婦の逆転人生。並みの語り手だとただの奇談で終わりでしょうが、中島敦の文体のごとく、キリッと引き締まった志ん朝の語り口が説得力となって話の世界に引き込んでいきます。

ところで私は、四十年前に聞いたラジオ以上の『抜け雀』に今もって出会えないでいます。宿屋夫婦も絵描きもまたその関係性もあの時のものが最高なのです。それは、漠然とした印象からそう言っているのではありません。一人一人の具体的な言葉の使い方が違うのです。なぜ、同じ落語家の同じネタで言葉が違うのか。それは、登場人物がその場を生きているからで、単にセリフを語っているのではないからです。これが一回こっきりの語り芸の本質的なところで、どういう人物が立ち上がってくるかは語ってみないとわからない。本落語教室生のみんなも、しっかりと体に入った話をする時は、そんな感覚をいだいているのではないかと思います。
怪談

来年秋のNHK朝ドラは、小泉セツがモデルのドラマになりました。言わずと知れた、文豪ラフカディオ・ハーン小泉八雲の妻です。
ハーンがアメリカの雑誌記者として来日したのは1890年。ところが雑誌社と揉め、契約破棄になってしまいます。たどり着いたのが松江、そしてそこで出会ったのが小泉セツです。翌年の秋には松江の寒さを恐れて熊本に異動するので、ハーンが松江で過ごしたのは一年あまりに過ぎませんが、その後のハーンの創作に多大な影響を及ぼし、よく知られた名作の数々は、ほとんど二人三脚で作ったようなものですから、縁結びの神様がセツに会わせるためにハーンを引き寄せたかのようです。
ちょうど40年前に、NHKが『日本の面影』というドラマで小泉八雲を描きました。去年亡くなった山田太一の脚本による傑作ドラマでした。八雲を演じたのは、ジョージ・チャキリス。映画『ウェストサイド物語』しか知らず、またあまりにその印象が強烈だっただけに、「はっ?八雲役がジョージ・チャキリス?」とあまりのビッグネームに驚くとともに「ちゃんとやーかや」と少々不安も覚えたのですが、どうしてどうして、ほかの俳優じゃ務まらないだろうと思える名演でした。来秋の朝ドラのキャスティングはこれからのようですが、だれがハーンを演じることになるのか大変に楽しみです。ちなみに小泉セツは檀ふみが演じていました。今度は主役ですから、セツの目から見たハーンが描かれることになります。『日本の面影』を凌ぐ傑作になりますように。
今年は奇しくも、代表作『怪談』が世に出て120年にあたります。それを記念したイベントも様々に企画されているようです。当落語教室も開設以来、機会あらばぜひ八雲の「怪談」を扱いたいと願ってきました。準備も進めていますので、順調にいけば年内には、皆さまに披露する時が来ることでしょう。オチがなければ落語とは言わないのですが、子どもたちにはそんな枠など関係なしに、物語の豊穣な世界を味わってほしいと願っています。それに子どもたちはこわい話が大好きですし。
八雲の怪談は、こわさも一級ですが、同時に、あるいはそれ以上に美しい、そして悲しい。昔話に材を取った体裁になっていますが、必ずしもそうとばかりは言えず、セツの語りにハーンの創作が加わって唯一無二の作品世界になっています。そんな語りに耳傾けるのも実に心地よいものです。「八雲をお願い」なんてオファーもお待ちしております。

出来心

落語には、泥棒が出てくる話がたくさんあります。「泥棒話」というジャンルがあるぐらいです。泥棒話は縁起が良いとされているので、高座でもよくかかります。タヌキの縁起の良さというのはまだ分かるのですが、泥棒はいったいどうしてそういうことになるのか。どうも「お客さんの懐をねらう」という物騒かつ謎かけめいた連想からのようです。かなりの無理筋ですが、シャレや冗談で成り立っている文化なので、固いことは抜きにするよりしょうがありません。
泥棒話の登場人物は、落語世界きってのぼんやりした人たちなので、盗みに入ったはずが逆に巻き上げられたり、けんかの仲裁をするはめになったりで、泥棒の仕事を完遂する例は皆無です。当塾落語教室生に泥棒話を持ちネタにしている児童がおりますが、これも典型的なダメダメぶり。あまりの不出来ゆえに親分からクビを言い渡されますが、あと一回だけチャレンジさせてほしいと頼み込みます。親分は情は解するもののぼんやりについては負けず劣らずですから、適当な家に盗みに入らせます。そこで起きるドタバタが無性におもしろい。
こんな泥棒話をいくつも聞いていると、江戸や明治の昔は悠長なものよ、気楽な泥棒稼業が成り立っていたのだから、などと思ってしまいそうですが、もちろん落語世界での話。庶民が夢想した究極の平和社会というファンタジーの中で棲息している人物です。「十両(今の貨幣価値で百万円程度)盗めば死罪」「一度盗めば敲き、二度盗めば入れ墨、三度盗めば死罪」という重い刑罰が科せられていたのがリアル江戸社会です。人情噺の傑作「芝浜」では、財布をネコババしようとした夫を妻が必死で守る噺ですが、露見したら重罪に問われると恐れおののくあの感覚が現実に近かったのだろうと思います。
ファンタジーなら徹底的にファンタジーであるべきで、落語の泥棒さんたちは、長い年月をかけて妖精みたいに造形されていったのでしょう。それゆえに聞いている側は、安心して楽しめるのです。
泥棒とは少し違いますが、詐欺師、ペテン師も落語には出てきます。「鰻(うなぎ)の幇間(たいこ)」という噺があって、幇間(たいこもち)の一八が「どこかで見たような男」を一生懸命ヨイショして飲食にありつこうとするのですが、だまされて払わされてしまいます。私は、昔からどうもこの噺が好きになれません。落語会に出かけて、この噺がかかると残念な気持ちになります。ずっとどうしてだろうかと考えていたのですが、一八をだます男のリアルさにあるのだと思い当たりました。妖精とは真逆の、腹の中ではまったく違うことを考えている人間のリアルな悪意。まあ、こんな写実的な噺も生き続けているってところが落語のすごさとも言えるのでしょうけれど。
子ほめ
今も、なのかもしれませんが、ひところ「ほめて育てる」という手法が学校でさかんに喧伝されました。研修でも、講師から「とにかくほめるところを探してほめなさい、どんなことでもいいから」と言われたことを覚えています。ほめて育てられた経験に乏しいまま教員になった身としては、どうも素直に従うことができず、最後まで苦手意識を抱えたままでした。ほめられれば悪い気はせず、意欲が増すのも事実ですから正しいことではあるんでしょうけど…

落語には、ほめる噺がけっこうあります。よく知られているところで言えば、「子ほめ」や「牛ほめ」。また、ほめるのが仕事の幇間(たいこもち)の噺も少なくありません。「子ほめ」は、実年齢より若く見える、とほめる噺。「牛ほめ」は、新築の家や新しく買った牛を決まり文句でほめる噺。どちらも、正直に感動を伝えるのではありません。ただ酒を飲む、あるいは小遣いをもらう、という極めて不純な動機でほめるのです。まったく心にもないことは、初めからバレバレで、ほめているのだかけなしているのだかわからなくなるというのが、これらの噺のおもしろさ。
興味深いことに、「酒飲ませろ」とか「こづかいちょうだい」と、真の目的がごく早い段階で相手に伝えられてしまうのですが、受け手側も初めからそれがわかっています。実際のところどう思っているかはどうでもよくて、「上手くほめることができたら、かなえてやろうじゃないか」という態度なのです。ほめ方が粋ならばよし、真情を吐露するなんぞ無粋なこと、と言わんばかりに。
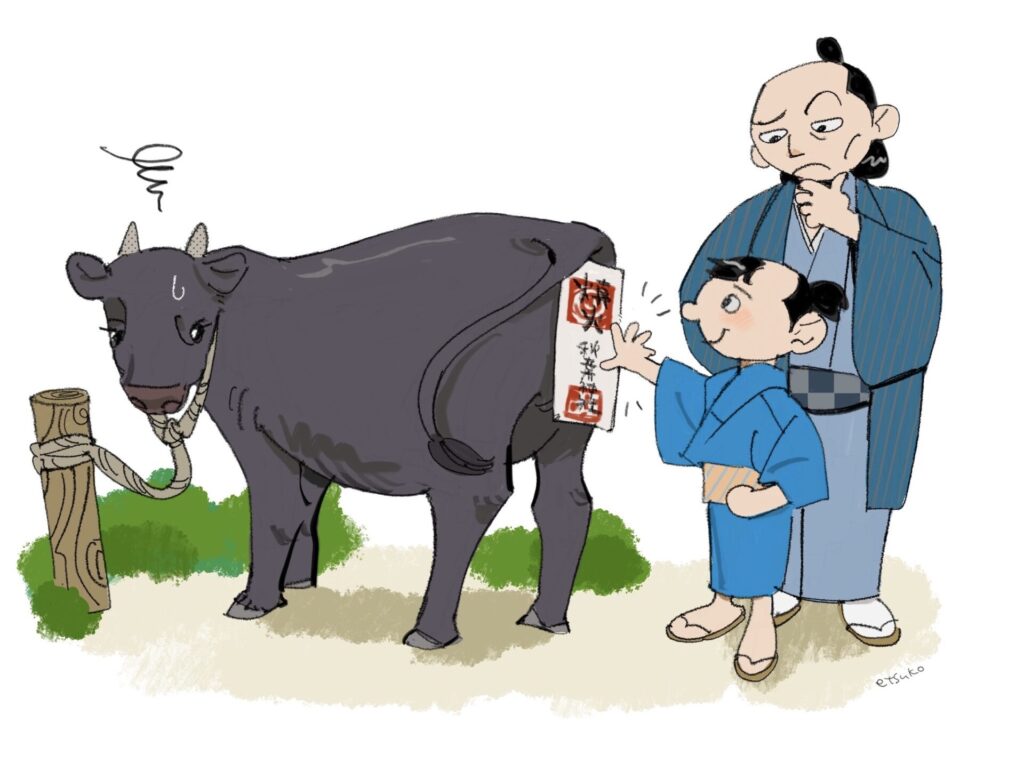
「牛ほめ」では、父親からカンニングペーパーを渡されただけで意味がまったくわかっていない与太郎が、トンチンカンにほめます。それをおじさんが「それを言うなら…だろ」といちいち直します。ということは、おじさんにはどうほめるのかがわかっていて、与太郎がきちんと定型をなぞるかどうかだけ気にしているのです。笑い話に加工してあるとはいえ、現代人とは異なる江戸庶民の価値観がうかがえる噺です。
幕末には多くの外国人が日本にやってきましたが、彼らの記録に「(江戸庶民は)だじゃれや言い立て(決まり文句)ばかりで、ちっとも話が前に進まない」とあるのを読んだことがあります。豊かと評するのが適当かどうかはわかりません。でも、子どもたちには、今とはひと味もふた味も違う人間関係を落語を通して感じ取ってもらいたいと思っています。これも一つの異文化交流と言えるかもしれません。
皿屋敷

この間、当塾の噺家さんに「ねえ、どうして落語ってたくさんはなしがあるの?」と聞かれて、どう答えたものか少し考えました。落語のネタ数は、300とも500とも言われています。これは古典落語の数ですから、日々作られている新作落語を加えれば膨大な数に上るでしょう。その中のいくつかは、幾多のふるいにかけられて古典に加わっていきます。冒頭の質問への答えとしては、何百年もかけて数え切れないほど多くの人が作り続けているから、ということになるでしょうか。
それだけに、落語ってよくもまあこれだけ多種多様な登場人物がいるものよ、と思います。前にタヌキも主要な登場人物としてご紹介しましたが、ご存命でない方たちもたくさん登場します。ゆうれいの出る噺、かなり多いです。これは、冷房のなかった昔の寄席小屋で、少しでも涼しくなってもらおうと落語家たちが工夫を凝らしたゆえに発達していったのかもしれません。有名なところでは、以前この欄にも登場してもらった幕末明治にかけての大名人三遊亭円朝の諸作。「牡丹灯籠」とか「真景累ヶ淵」など、文庫本なら一冊ゆうにあろうかという大作を何夜にも分けて、今でも夏になると高座にかかります。私の好みは、何と言っても昭和の大名人六代目三遊亭圓生で、何度聞いても背筋が寒くなります。

当塾落語教室も、夏を前にぼちぼちゆうれいネタに取り組もうと考えています。もちろん円朝のホラーではありません。怪談さえ笑い話に変えて、ゲラゲラ、ヘラヘラとこの世とあの世を行き来するのが落語の真骨頂。「皿屋敷」もそんな噺の一つです。原典は「番町皿屋敷」。横恋慕した代官の怒りを買って殺されてしまったお菊さんが夜な夜な井戸から出てきては、言いがかりの元になった皿を数えます。九枚まで聞くと呪われてしまう、という何とも恐ろしい話ですが、「それじゃあ、そこだけ聞かなかったら大丈夫だろう」と考える好奇心旺盛な連中が、お菊の出てくる井戸を見に行くというのが落語版「皿屋敷」。さて、若い衆がどうなるか、今夏、当塾の誰かが高座にかけるかもしれませんので、ぜひご期待ください。陰惨な悲劇をここまで喜劇に転換できるのか、と落語の底力に感嘆します。
先日、たまたま落語教室生が稽古場に五人集まったので、試みに同じ小咄をそれぞれでアレンジして演じてもらいました。登場人物は全員泥棒です。まったく同じ咄なのに演ずる子によってずいぶん印象が異なるのがおもしろく、また新鮮でした。明るくカラッとした泥棒がいたかと思うと、サスペンスタッチの渋い泥棒がいたり。それぞれの子どものもっている雰囲気やその時々の気持ちなどが、固有のイメージを作り出すのです。またやる機会があったら、ゆうれいの小咄をしてみるのもおもしろそうです。お茶目、まじめ、おてんば、物静か、いろんなゆうれいが集って、教室が愉快でハッピーなゆうれい屋敷になることでしょう。
あわてものの大社さんまいり/堀之内
当塾落語教室の稽古を見に来てくださったご縁で、出雲かんべの里の語り部さんと親しくなりました。同所の民話館で、「子どもの語り部」が語る催しがあり、先月出かけてきました。民話を語る文化を次世代に継承すべく育成にも注力されていることを今回初めて知り、同じ話芸育成に関わる者として学ばさせてもらいたいと思いました。民話は「かたる」、落語は「はなす」、違いはあるもののかなり近しい関係にあるような気がしていましたが、訪問時にいただいた『出雲かんべの里の語り』(悠書館2016年)に収録された作品を読んで、改めて民話と落語は地続きだと感じました。
一例を挙げると、「あわてものの大社さんまいり」という民話があります。あまりに落ち着きがなく、失敗ばかりの亭主にあきれた女房が「信心でもしたら」と勧めると、亭主もその気になります。ならば明日大社さんにお詣りしようと日の明るいうちから寝てしまう。万事がその調子なので、まともに事が進むはずありません。どたばたの連続が実にばかばかしくておもしろい。
この出雲大社が江戸堀之内のお祖師(おそっ)さまになるとそのまま落語の「堀之内」です。堀之内は、あわてものがしでかす奇行を並列に置いたギャグのオムニバスなので、現代のそれは、落語家たちの工夫を凝らしたギャグが積み重なって高速で流れていきますが、大社版はあっさりとしていて、原型に近いのではと思います。語り手は、明治四十年生まれ斐川町の青木清吉さんです。青木さん本人あるいは出雲在住のどなたかが落語「堀之内」を聞いてアレンジされたのか、それとも広く分布した語りの中から落語が採り入れて洗練されていったのか、経緯をたどることはできませんが、落語と民話が混ざり合っていることの証拠と言えましょう。

当塾落語教室生にもいつか取り組んでもらおうと考えていますが、やるなら出雲大社版と思っています。「堀之内」は人気演目の一つで、多くの落語家が高座にかけます。ですから、落語文化が絶えない限りこの噺がなくなることはないでしょう。でも、出雲弁で語られる「あわてものの大社さんまいり」は、放っておいたら消えてしまいます。テキストで残ったとしても、「語り」と縁が切れてしまえば、それは本来の姿とはまったく別物です。
堀之内…「ああ、何だよ、これ弁当かと思ったら、枕が出てきたよ。おう、このやろう、恥かかせやがって」
あわてものの大社さんまいり…「こな、だらくそ。弁当かと思ったらまくらだがな」
やってみたいですねえ。今の小学生に出雲弁を語らせるなんて、外国語学習みたいなものだとは承知しておりますが。
死神

もうずいぶん前のことになりますが、この話を初めて聞いたとき、これまで聞いてきた落語とはずいぶんと趣が異なっているのに驚きました。主な舞台は江戸で、完全に和の話なのですが、どこか洋の空気をまとっています。子どもの頃にテレビのロードショーでよくやっていた恐怖映画に通じる不気味さとでもいいましょうか。
借金まみれになった男が一度は死のうとするのですが、現れた死神に医者になって金儲けをしないか、と持ちかけられます。病人の枕元に死神がいたら助からないが、足下にいれば呪文で追い払える。運にも恵まれて男の新規事業は大当たり。瞬く間に大金持ちになります。ところがそうそう幸運は続きません。立て続けに枕元にいる死神ばかりにあたり、覚えてしまった浪費癖とも相まってあっという間に転落していきます。起死回生に放った奇手が死神の逆鱗に触れ、男はとうとう…
この話を作ったのは、幕末から明治にかけて活躍した大名人三遊亭円朝です。円朝は、なんとグリム童話の中から題材を採ってこの話をこしらえています。これを知ったとき、どこか洋風な感じがした理由はこれかと、長い間の謎が解けた気がしました。
小佐田定雄さんの『5分で落語の読み聞かせ』にもこの話は採られています。不気味さはうんと薄められ、子どもたちが聞いて楽しめるように工夫されています。落語の幅広さ、奥深さを感じるにはいい話だと思い、以前ある子に勧めました。けっこうしつこく。でも、ついに「やります」とは言いませんでした。理由は教えてくれませんでしたが、察するに、話が気に入らないとか難しいということではなく、主人公が死ぬことになる結末に近寄りがたさを感じているようでした。高座にかけるに至らなかった話にもそれぞれに物語があります。
この「死神」、落語家の創作意欲を駆り立てるようで、演者によって様々なパターンが試みられています。有名なところでは故柳家小三治のアレンジで、絵本にもなっています(『しにがみさん』教育画劇)。落語好きの知人は、幸運にも高座で小三治師のそれを聞き、いまだにあれを超える落語に出合わないと言います。また、噺家によっては、その日のお客さんの雰囲気によって、バッドエンドとハッピーエンドを使い分けるといいます。こういう離れ業が成立するのも、噺は噺家のもの、原作に忠実なんてことにまったく価値を置かない落語ならではです。
さて、当塾落語教室生がいつか「死神をやりたい」と言ってきたら、私は「待ってました!」と言ってしまいそうですが、まああんまり期待しないで待つことにします。
狸賽
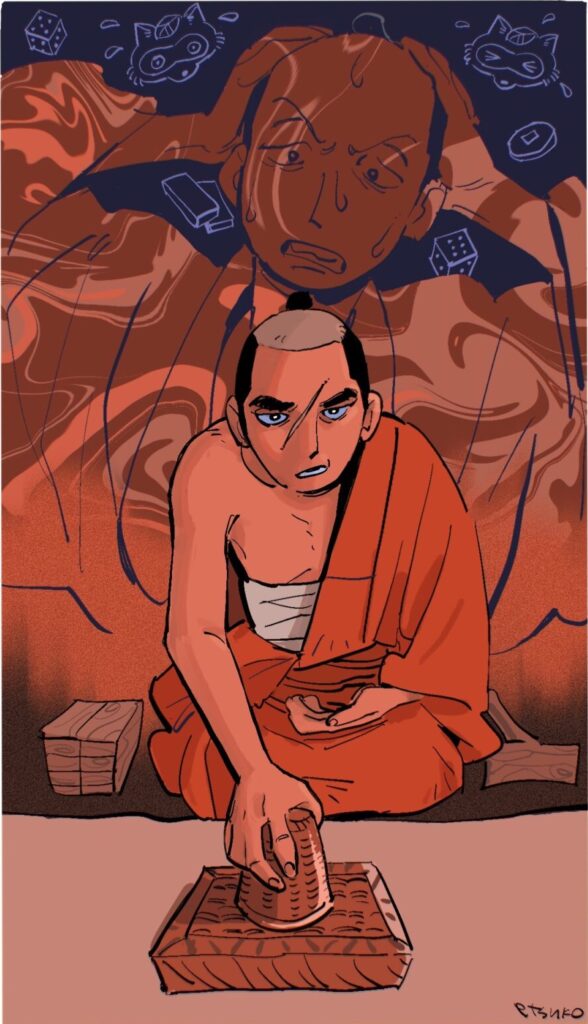
落語のどんなところがいいか、と聞かれて「だってたぬきやきつねが出てくるでしょう。いいよねえ」と語ったのは、名人故古今亭志ん朝さんです。ちなみにジブリ映画「平成狸合戦ぽんぽこ」のナレーションを務めたのも志ん朝さんでした。
動物が出てくる落語はたくさんありますが、抜きん出て多いのはやはりたぬき
でしょう。人を化かす上にどこかユーモラス、落語がこんな特異なキャラクターをほっておくはずはありません。当塾もたぬきをメインキャラクターにしていますが、これは考案者が落語の縁起担ぎに塾のそれを重ねたためです。「化ける」は「上昇する」「成長する」につながり、縁起のよいものとされているのです。それゆえ寄席ではたぬきネタはかかりやすく、今回のお題の「たぬさい」もこれまで何度も聞きました。塾のたぬきにも、算数も落語も大いに上昇、成長しよう、という願いがこめられています。このたぬき、まだ名前がありません。思いつかれた方、ぜひお寄せください。
「たぬさい」は「たぬきのさいころ」を縮めたもの。あるばくち打ちが恩返しに来たたぬきをサイコロに化けさせて一もうけを企むという話です。たぬきの純な思いを悪用するのですから、現代で言えばこの男、特殊詐欺グループのリーダーみたいな悪党ですが、そこは落語なので、限りなく不徹底で悪人になりきれません。そもそも「たーちゃん、次は一、一だよ、一お願いします。」など手の内をさらけだす指示をおおっぴらにするのですから、いくら鈍い仲間たちでも気づきます。初めは上手くいって儲けますが、すぐにぼろを出してしまいます。よせばいいのについ調子に乗ってしまう男と大まじめに尽くそうとするたぬきのやりとりがたまらなくおもしろい話です。
子どもとたぬきは相性がいい、そう思います。大人に比べてどことなく丸みを帯びた顔や体型だし、人をだますわりにはずるい感じがしないという点でも子どもが演じるたぬきはよくはまります。ちょっと複雑な心情を描くので、これまであまり積極的に取り上げてきませんでしたが、子ぎつねと子だぬきが登場するとてもすてきな小咄があります。当塾の噺家とチャレンジしてみたいと思っています。「活活こども寄席」の成長のためにも「化ける」話を。

転失気

「てんしき」と読みます。どういう意味なのかは、ひとまず置いといて。
昔、何かの本で読んだのですが、巨匠黒澤明は、スタッフや俳優に問いかけたとき、あいまいな返事が返ってくると「知らないことは、知らないと言いなさい」と強く叱ったそうです。新人ならいざ知らず、それなりの立場を得た人にとって、「知らない」は言いにくい。いい映画を撮りたければ、つまらぬこだわりを捨てよ、という黒澤明の端的なメッセージです。やはり現代を代表する映画監督のクリント・イーストウッドは、今も映画を撮るとき、誰彼構わず「私は何にも知らないので教えてください」と言うのだそうです。
もしかすると、この「知らない」の尊重がよい仕事をする秘訣なのかもしれない、と考えるのですが、もちろんだれもがそんなに謙虚になれるはずもなく、時と場合によっては妙なプライドを大事にして威圧的な態度を取ってしまうことだってありましょう。これが落語では格好の攻撃対象になります。それなりの立場にある人、武士、お坊さんなど、そういう人物造形をされて、徹底的に茶化されます。
自他共に認める「物知り」である和尚様。物知りと讃えられるがゆえに「知らない」が言えなくなってしまいました。お医者様の診察を受けたら、
「時に和尚様、転失気はございましたかな?」
と尋ねられました。和尚様、このいかにも漢語調の言葉の響きに「てんしきとは何ですか」と聞くことができません。その場は適当にあしらうものの、気になってならず調べようとするのですが、さすが落語の登場人物、姑息な手段に出ます。小僧の珍念さんに調べに行かせるのです。「自分は知っているんだが、お前の修行のために」と。ミスターお為ごかしです。
初めは和尚様の言うことを信じて聞いて回っていた珍念さん、ついに真相に気づきます。ここで素直に「和尚様、てんしきとは…」と申し上げるような人物は子どもといえど落語には出てきません。ここからお医者様を交えて和尚様と珍念の丁々発止のやりとりがこの話の聞き所です。最後は珍念にギャフンと言わせられるのですが、そんな和尚様を珍念はどこか慕っているふうなのが、またまた極めて落語的です。子どもにそんな複雑な関係が演じられるのかと思われるかもしれませんが、子どもが語るから描けるということもあるなあ、と高尾小の子どもたちを見ていて思いました。
ちょっと、いや、かなり尾籠な話なのですが、子どもたちにぜひやってもらいたい演目の一つです。立場はどんなに隔たりがあったとしても人と人、友達になれないはずはない、心のどこかにそんな思いを潜ませてくれるような気がするので。
さて、転失気のほんとうの意味は。
それは活塾の噺家さんがいつか高座にかけるまでのお楽しみ、ということで。
まわりねこ

これも高座で聞いたことがありません。なぞなぞをつないだような、よく言えばかわいらしい、悪く言えば単純極まりない話なので、今の落語家が取り上げる気にならないのもわかる気がします。
ネコが生まれたので名前を付けようとします。どうせなら強い名前にしようと相談すると、「強いといったらトラだ」。そこから無限ループのなぞなぞ開始です。「トラより強いのは?」
「リュウ」、「リュウより強いのは?」、「風」、「風より強いのは?」…
調べてみると、その昔高座にかかっていたときは、弁慶とか義経などが登場しています。落語が隆盛を誇った明治大正期で強いものの代名詞と言えばその二人になるのでしょうね。もちろん、今の子どもたちにその二人の名前を言ってもピンときません。小佐田定雄さんは『5分で落語の読み聞かせ』で楽しい工夫をしています。相談相手を日本各地の親戚にして、それぞれのお国言葉で強い名前の提案をさせたのです。「そら強いいうたらトラやろ、なんちゅうたかて、タイガースは日本一やさかいな」と大阪のおじさんに言わせたかと思うと、「リュウだぎゃー」と名古屋のおばさんに反論させるという具合です。
方言で大受け
この話を高尾小「にこにこ寄席」で最初に演じたのは、三年生の女子児童でした。当時は、三年生と四年生の複式学級の子どもたちだけで落語活動をしていました。始めたばっかりの彼女にとって、話を覚えることはかなり荷が重かったようです。苦手意識もあったかもしれません。勧めた話をなかなか覚えようとせず、一度叱ったことがあります。どちらかといえばいつもニコニコ朗らかにしている彼女がその時ばかりはしゃくり上げて泣き、「怒らなくてもいいじゃないですか」と抗議しました。「自分だってがんばっているのに先生は分かってくれない」そんな悔しい思いを懸命にこらえていることにようやく気がつきましたが後の祭りでした。その後どう慰めたか、または何も言えなかったのかよく覚えていませんが、気分一新をはかる意味で与えたのが「まわりねこ」でした。なぞなぞの繰り返しですから覚えやすくもあったのでしょう。表情もすっかり以前のにこやかさを取り戻しました。ただ方言には手こずりました。大阪、名古屋、福岡、北海道、高知それぞれの独特な言葉やイントネーションは、そう簡単に表現できません。そこで私は、クライマックス部分を「出雲のおばば」に代え、出雲弁にしてみました。モデルは、母や祖母です。
「はあ?、ネコの名前に壁だことのだらつけな(ばかばかしい)。なんぼがんじょ(頑丈)な壁だけんて、ネズン(ネズミ)が出てきて噛んさがったら(噛みでもしたら)、ひとたまあ(ひとたまり)もないがの(ないじゃないか)…(まだまだ続く)」
彼女もこれには面白がって、ついにできあがり。これはどの会場でも想像以上にドッカンドッカン受けて、彼女の代表作になりました。今も後輩たちが受け継いでいます。
この「まわりねこ」は想像以上の効果をもたらしました。彼女はすっかり自信を付けて、その後は、「反魂香」や「牛ほめ」など、言い立て(一連の決まった長台詞)が妙味の落語ネタを得意とするようになるのです。「どうやって覚えてるの」と感心して聞いてみましたが、「えへっ」と笑うばかりで教えてくれませんでした。
茗荷宿

「みょうがを食べるともの忘れする」今では、そんな言いならわしを知っている子どももいないかもしれませんが、私が子どものころは、みょうがが食卓に登場すると合い言葉のように母親が言っていました。あの独特な香りがどうも苦手で、もの忘れする上にこんな臭い食べ物をなぜ食べるのかと不思議でしょうがありませんでした。今では、そうめんでも酢の物でも刻んだみょうがが乗っているとそれだけで食欲も気分も上がりますが。
茗荷の由来
お釈迦様の弟子で、もの忘れ名人の槃特(はんどく)さんがこのいわれの由来です。自分の名前すら忘れるので名荷(みょうが)つまり名札をつけさせてもそのことさえ忘れるという徹底ぶり。槃特さんが亡くなるとお墓の周りにある草がたくさん生えてきました。故人にちなんで「茗荷(みょうが)」と名付けられ、先のいわれが誕生したというわけです。植物にとっては明らかに不当な言いがかりですが、あの香りとエピソードがしっくりきたものか、そこはかとないユーモアを湛えて今に伝わっています。
落語の「茗荷宿」は、このいわれを使ったお話です。宿屋の夫婦が一計を案じ、特産の茗荷を様々に料理して客に出し、忘れ物をせしめようとします。高尾小学校の女流落語家青葉亭ふらわーさんとそれを受け継いだ夕焼けさんがこの話を得意にしていて、「茗荷ごはんに茗荷の酢の物、茗荷汁に茗荷の天ぷら…」と並べていき、はては「茗荷プリンに茗荷ジェラート」と自分好みに創作して笑いを誘います。
さて、果たして宿屋夫婦の思惑通りにいったのか、これはこの話の落ちにあたり、あざやかなことこの上ないのでここに記すは野暮というもの、気になる方は「にこにこ寄席」に行かれるなり本で調べるなりしていただければと思います。
川端誠落語絵本
この話はめったに高座にかかりません。私も高座では一度も聞いたことがありません。小学生のころ、テレビで一度見たきりです。もう十年以上前になりますが、絵本作家の川端誠さんと話したときのことです。話題が子どもたちに人気の落語絵本シリーズに及んだので、「次の作品は?」と尋ねると、「茗荷宿にしようかと思っています。」と言われました。私がとっさに落ちを語りますと川端さんは目を丸くして、「この話を知っている人に初めて会いました。」とおっしゃいました。高座で聞く機会などまずないし、自分はテレビで一度見たきりだ、とも。川端さんと私は同世代です。話を聞くと、どうも同じ番組を見て、同じように落ちの見事さに魅了され、ずっと記憶にとどめいたということのようでした。

消えたところで誰も何も思わない他愛のないお話かもしれません。しかし、それを何十年も温め続け、伝える値打ちのある話として絵本に残した川端さんの思いを私はとても尊いと思います。そして「にこにこ寄席」という高座にかけて、お客様に伝え続けている高尾小の子どもたちもまた、文化を支えるとても尊い活動をしていると思うのです。
ちなみに、川端誠さんの『みょうがやど』は、シリーズ15作目として2012年クレヨンハウスから出版されています。
じゅげむ

最も有名な落語といえば、「まんじゅう こわい」と双璧をなすのが「じゅげむ」です。おしょうさんにめでたい名前をつけてもらったのはいいが、あまりに長い名前で呼ぶだけでたいそう時間がかかる。それがために起きるドタバタを笑う滑稽話です。私がいちば ん頼りにしているテキストは、小佐田定雄さんの『5分で落語の読み聞かせ』(PHP)ですが、これには続編が2冊あ ります。小佐田さんは、それぞれの巻頭に「じゅげむ」とその改作を載せています。一巻では「じゅげむじゅげむ…」と名を呼ぶ間にたんこぶがひっこむ原型を載せるも、 続編では小佐田流アレンジが冴え渡ります。 テストで名前を書いていると時間切れになる、選挙カーで名前を連呼していたら落選する、ボクシング選手になったらリングアナウンサーが名前を呼ぶ間に相手が怒りだ してしまう、など。「じゅげむ」の職業や立場を替えるだけでおもしろい エピソードが生まれます。
子どもたちにとってこれほど語りやすい演目は他 にありません。なぜなら「じゅげむじゅげむ、ごこうのすりきれ、かいじゃりすいぎょの…」と名前を覚えてしまえば、話の大半を覚えたことになります。あとはお母さんが朝起こすとか、友達とけんかするとか場面を変えて繰り返します。高尾小学校では、代々中学年が十八番にしてお客様に披露してい ます。
子どもが演じる「じゅげむ」
前座話としてあまりに有名過ぎるためか、実際の寄席や高座でこの「寿限無」を聞いたのはたった一 度しかありません。前座であってもプロとアマでは 歴然とした違いがあるものですが、残念ながら、あ まりおもし ろく思えませんでし た。高尾小の子ども たちの方がよっぽどおもしろい と思いました。話の 巧拙ではありません。落語は、子どもが主役の話が 意外と少なく、「じゅげむ」はその意味では貴重な 話です。子どもを演じるには、やっぱり子どもがい ちばんしっくり きます。「じゅげむじゅげむ…」と たどたどしくも一生懸命語っている姿は、ほほえま しさがベースにあるためか、笑いを誘引しやすいよ うです。それに、小さな子どもの声でリズミカルな「じゅげむ」を聞く、それ だけでも気分が高揚する のかもしれません。いつでもどこでもよく受けます。
今年、三遊亭白鳥さんの「寿限無」を聞く機会が ありました。白鳥さんは、創作落語の名手として人気があり、ちょっとぶっ飛んだ笑いを作らせたらピ カイチです。彼が正統「寿限無」をするはずなく、 案の定「スーパー寿限無」とい うタイトルで話を始めました。めでたい名前をつけてもらうために相談に行った先は、白鳥師匠。「今の人類に最も必要なものは何だ。愛だろう。愛はフランス語でジュテーム。二つ重ねてジュテームジュテーム。」という調 子。館内大爆笑でし た。
どんなアレンジにも応じて新しい笑いを作り出す、というよりアレンジをさせずにはおかない「じゅげむ」は実に懐の深い偉大な話であります。
まんじゅうこわい

「じゅげむ」と並んで最もよく知られた話です。この間、塾に来た一年生の子に「落語って知ってる?」と聞いたら、「まんじゅうこわい」と得意そうに答えました。
「こわいものは?」と聞かれた男が、本当は大好きなまんじゅうをこわいと言って、友達にいたずらさせてまんまとせしめるという話です。起承転結がはっきりしていて子どもにもわかりやすく、演じやすいネタです。高尾小学校でも代々だれかが持ちネタにしています。この話の見所は、こわくて逃げ出すと思って投げ込んだまんじゅうをおいしそうにパクパク食べるところです。高尾小で最初に演じたのは、もう高校生になっているH君です。なかなかのアイデアマンで、食べるまんじゅうを地元のお菓子屋さんの主力商品にして、いかにもそれを食べているふうに演じました。「おっ、これは松葉屋さんの、噂の生どらだ。これ好きなんだよなあ。」と言いつつ、いっしょに口に入れてしまった乾燥剤を出すような細かな所作まで入れて。その地では誰もが知っているお菓子なので、お客さんも大喜びです。拍手つきの笑いを浴びてH君も大満足でした。話はそれで終わりません。そのお菓子屋さん、噂を耳にされたようで、後日、「うちの宣伝をしてくださって、どうもありがとうございます。」と「噂の生どら」はもとより、他のお菓子もどっさりと学校に届けてくださいました。給食の時だけでは食べきれず、全校児童(と言っても十名足らずですが)持ち帰って家族へのお土産にしました。
子どもたちがこの展開を一回きりで終わらせるはずがありません。奥出雲町外での高座では、ご当地の代表的なお菓子を調べて、柳の下の泥鰌をねらいました。落語はどこでも大いに受けましたが、泥鰌はそう簡単にいません。でも、こんなことがありました。大社町に呼ばれたとき、H君は意欲満々で大社名物「俵まんぢう」を大いに褒めておいしいおいしいと食べてみせました。かわいい子どもたちの落語に皆さん大喜びでしたが、泥鰌はなし。でも、高尾小の子どもたちと高尾という地区に興味を持たれたようで、後日バス仕立てで高尾小を訪問されました。その時の子どもたちへのお土産がどっさりの「俵まんぢう」だったのです。時間差の泥鰌もたいそうおいしかったです。

「まんじゅうこわい」は、上方には三十分超の大ネタ版があります。怪談になったそれを聞くと、こんなダイナミックに話が変化するのかと驚きます。変幻自在の上方落語、そういえば以前高座で七代目笑福亭松喬さんの『チョコレートこわい』というのを聞いたことがあります。もしまた機会があったら、今の子どもたちの好物でやってみるのもいいかなと思っています。「ポテチこわい」とか「グミこわい」とか。






